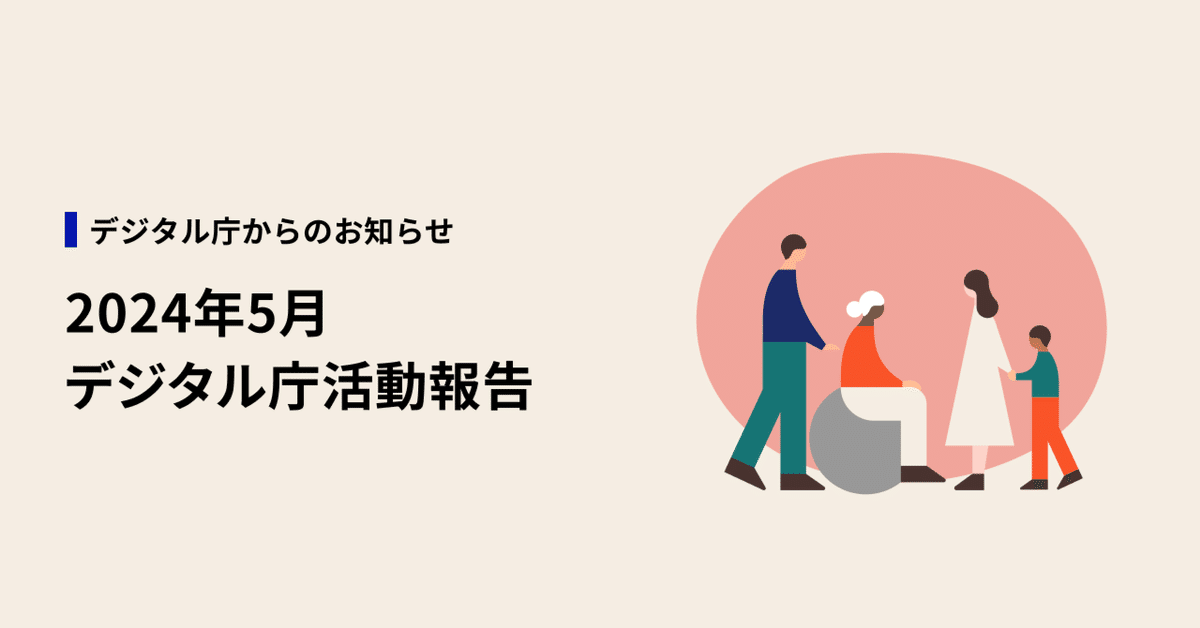
デジタル庁 2024年5月の活動報告
デジタル監の浅沼です。
2024年5月のデジタル庁の政策、サービス、組織に関する主な活動、およびプロジェクトの進捗や成果について共有します。
1.生活者・事業者・職員にやさしいサービスの提供
マイナンバーカードの救急業務活用の実証実験を宮崎県都城市などで開始しました。救急車利用時に、マイナンバーカードを活用して救急業務をおこなうことで、救急業務の迅速化・円滑化を目的としています。傷病者の医療機関への早期搬送と早期医療介入に結びつくことを目指しています。
2024年5月27日、マイナンバー法等改正法(改正マイナンバー法)が施行されました。これらの施行によって、大きく下記4点が変わりました。
1.海外でマイナンバーカードを継続利用することが可能に
国外に転出(引越し)する場合に、マイナンバーカードが失効することなくお持ちいただけるようになりました。また、海外でもマイナンバーカードが作れるようになりました。
2.マイナンバーカードの「かざし利用」規定が明確に
マイナンバーカードの利用方法のうち、暗証番号を入力しない「かざし利用」に関する規定が明確化されました。今後も図書館カードとしての利用や避難所への入退場の際の利用など、「かざし利用」でのカード利用を推進していきます。
3.各種免許や国家資格等のオンライン・デジタル化へ
医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士をはじめ、80近い国家資格などの資格について、マイナポータルを通じてオンラインサービスを利用いただけるようになります。
4.公金受取口座の登録方法を拡充
日本年金機構と連携し、ご高齢の方やデジタルに不慣れな方でも年金受取口座を公金受取口座として簡易に登録可能になります。マイナンバーカードを用いて本人確認をする事業者に、チェックポイント等を周知するための事務連絡を関係省庁に通知しました。また、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)で無償提供しているICチップ読み取りを行うPCアプリの利用を推奨しています。デジタル庁でもICチップ読み取りを行うスマートフォンアプリの開発提供を検討していきます。
定額減税しきれないと見込まれる方に対する給付を円滑かつ効率的に行うために、自治体向けに「調整給付のための算定ツール」の提供を開始しました。
5月23日に、自民党デジタル社会推進本部から「デジタル・ニッポン2024」をご提言いただきました。少子高齢化や人口減少など社会課題の解決、デジタル領域の産業振興、自然災害やサイバー攻撃対応など持続可能性の確保に向け、デジタル政策・データ戦略を着実に社会実装するとともに、デジタル庁の体制強化を図っていきます。
デジタル庁では、マイナンバーカードの普及や登録状況をお伝えするため、ダッシュボードを公開しています。2024年5月より、表示する統計の値を交付数から保有数に変更するなど、データの定義の見直しをおこない、掲載を再開しました。
岸田総理大臣と米Apple社CEOのティム・クック氏の間でテレビ会談がおこなわれ、マイナンバーカードの機能をiPhoneに搭載することについて、確認がおこなわれました。iPhoneへの搭載の時期については、来年の春にリリースできるよう、取り組みを進めます。iPhoneへは、マイナンバーカードの機能のうち、現在Androidで搭載済みの、様々なオンライン申請やログインを可能とする電子証明書の機能だけでなく、マイナンバーカードの券面記載事項も搭載し、氏名、住所、年齢などを、オンラインでも対面でも、証明できるようにしていきます。
ダッシュボード開発において品質向上や設計の効率化に貢献するため、実践ガイドブックとダッシュボード開発ツールのPowerBIのチャート・コンポーネントライブラリを公開しました。実践ガイドブックは、デジタル庁で実践してきた政策データダッシュボードの作成時の知見に加え、行政職員や民間有識者のダッシュボードやデータ可視化に関する意見を反映したものを整理し、体系化したものです。今後もデータの可視化や分析に関する知見を公開し、EBPM(Evidence-based Policy Making)の推進を進めていきます。
マイナンバーカードを医療費助成の受給者証や診察券として利用できるようにする実証事業について、先行自治体を決定しました。自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH)を開発し、病院等医療機関において、マイナンバーカード1枚であらゆるサービスを利用できる環境を整えていきます。
デジタル庁では、デジタル政策やサービスをより多くの方々に届けるために、日々コミュニケーションの改善を図っています。デジタルの現在や未来の情報を届けるオウンドメディア「デジタル庁ニュース」で、複数の動画を公開しました。またデジタル庁noteにて、改正マイナンバー法に関する記事も公開しました。
2.デジタル基盤整備による成長戦略の推進
日本とEUの間でのデジタル関連の協力を進めるため、デジタル庁と欧州委員会との間でデジタル・アイデンティティに関する協力覚書(MOC)の署名式をおこなうとともに、「第2回日EUデジタルパートナーシップ閣僚会合」を共催し共同声明を採択しました。
デジタル庁では、デジタル社会の実現に向けた重点計画を踏まえ、AIの実態と動向を把握し、リスクと必要な対応策を特定したうえで、官民における適切な活用の検討を進めています。
昨今の生成AIなどの技術革新により、さまざまな利点を得られるようになってきており、政府としても、このような技術の動向を見極めつつ、関係省庁における生成AIの業務利用について、第10回デジタル社会推進会議幹事会・書面開催など議論を重ねてきました。これまでの議論の経緯も踏まえ、デジタル庁では、2023年12月より生成AIの適切な利活用に向けた技術検証を実施。2023年度の検証結果の全体的な内容と、検証で得られた具体的な生成AIへの入力文のサンプル、一部検証に用いたテストケースを公開しました。自動運転、ドローン、サービスロボットなど地域のモビリティを支える技術の事業化に向けた「モビリティ・ロードマップ2024(仮称)」の策定をするため、モビリティワーキンググループを開催しています。第4回となる今回、「モビリティ・ロードマップ2024(仮称)」のとりまとめの方向性についてや、「AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキンググループ」の検討状況について、意見交換をしました。
3.安全・安心で強靭なデジタル基盤の実現
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(2023年6月9日閣議決定)を踏まえ、国・地方を通じたデジタル基盤に関して、全体最適かつ効率的なネットワーク構成を検討するため開催しており、この度検討会最終報告書を公開しました。
5月2日:デジタル庁ニュースで「農林水産省とこども家庭庁におけるGSSユーザーの声」に関する動画を公開
「農林水産省とこども家庭庁におけるGSSユーザーの声」を紹介する動画をデジタル庁ニュースで公開しました。
日本の行政機関は各府省庁にLANシステムやネットワークの整備をおこなってきたため、省庁間の連携に課題を抱えていました。また、セキュリティ対策の課題からテレワークなどの柔軟な働き方への対応も遅れていました。
こうした課題を解消するためデジタル庁は、最新技術を採用し、政府共通の標準的な業務実施環境を提供するサービス「GSS」を開発。各府省庁の業務実施環境の統合を順次進めることを目指し、すでに10府省庁で導入が進んでいます。
5月2日:河野デジタル大臣が2024年OECD閣僚理事会に出席

河野デジタル大臣は、5月2日及び3日の日程で、フランス・パリで開催されたOECD(経済協力開発機構)閣僚理事会に出席しました。
OECD加盟60周年となる本年、日本は「変化の流れの共創:持続可能で包摂的な成長に向けた客観的で高い信頼性に裏づけられたグローバルな議論の先導」をテーマとして開催されたOECD閣僚理事会で議長国を務めました。デジタル庁からは河野デジタル大臣が出席し、3日におこなわれた「DFFT (※1)、データガバナンス、セキュリティ」のセッションで議長を務め、広島サミットの承認を受けて設立したDFFT/IAP(※2)の方針及び国際データガバナンスに関する議論を牽引しました。
※1 DFFT(Data Free Flow with Trust):信頼性のある自由なデータ流通
※2 IAP(the Institutional Arrangement for Partnership):DFFT具体化のための国際メカニズム
5月5日:河野デジタル大臣が欧州・中東を訪問

河野デジタル大臣は、2024年4月29日から5月5日まで、ベルギー、オランダ、フランス、サウジアラビアを訪問しました。
日本とEUの間でのデジタル関連の協力を進めるため、デジタル庁と欧州委員会との間でデジタル・アイデンティティに関する協力覚書(MOC)の署名式をおこなうとともに、「第2回日EUデジタルパートナーシップ閣僚会合」を共催し共同声明を採択しました。
5月7日:衛生画像などを使った固定資産の現況調査の先進事例を公開
地方自治体の固定資産の現況調査にあたり、衛星画像の活用やAIによる画像解析などの先進事例が総務省より紹介されています。最新技術の活用、アナログ規制の見直しにお役立てください。
5月9日:デジタル庁ニュースで「ガバメントクラウド」に関する動画を公開
「ガバメントクラウド」を紹介する動画をデジタル庁ニュースで公開しました。
デジタル庁CCO(チーフクラウドオフィサー)の山本教仁が、ガバメントクラウドが政府や地方公共団体にもたらすメリットや現状の課題、「モダンなアーキテクチャ」の重要性などを紹介しています。
5月13日:デジタル庁・行政における生成AIの適切利活用に向けた技術検証を実施
デジタル庁では、デジタル社会の実現に向けた重点計画を踏まえ、AIの実態と動向を把握し、リスクと必要な対応策を特定したうえで、官民における適切な活用の検討を進めています。
これまでの議論の経緯も踏まえ、デジタル庁では、2023年12月より生成AIの適切な利活用に向けた技術検証を実施。2023年度の検証結果の全体的な内容と、検証で得られた具体的な生成AIへの入力文のサンプル、一部検証に用いたテストケースを公開しました。
また、本検証により得た知見もデジタル庁Techブログにて全3回で掲載しています。
5月16日:デジタル庁ニュースで「4人の神戸市職員が語る行政×データ利活用」に関する動画を公開
「行政×データ利活用」を紹介する動画をデジタル庁ニュースで公開しました。職員が自らデータを分析、可視化し、共有できる仕組みを構築するなど、行政データの利活用に取り組んでいる神戸市。これまでの取り組みや、データ活用を実践したからこそ分かったことについて紹介しています。
5月16日:マイナンバーカードの保有数を掲載

デジタル庁では、マイナンバーカードの普及や登録状況をお伝えするため、ダッシュボードを公開しています。
2024年5月より、表示する統計の値を交付数から保有数に変更するなど、データの定義の見直しをおこない、掲載を再開しました。
5月16日:デジタル庁noteで「目が見えなくても行政手続ができる社会をつくるデジタル庁アクセシビリティアナリストの役割」に関する記事を掲載

デジタル庁noteで「目が見えなくても行政手続ができる社会をつくるデジタル庁アクセシビリティアナリストの役割」に関する記事を掲載しました。
デジタル庁では、「誰一人取り残されない、人にやさしいデジタル社会の実現」を目指しています。そのためには、障害のある人やご高齢の方などを含むすべての方が、ウェブで提供されている情報やサービスをスムーズに利用できることが不可欠です。これらを実現するため、デジタル庁ではアクセシビリティアナリストがウェブアクセシビリティの確保・維持・向上のため継続的に取り組んでいます。本記事ではデジタル庁のアクセシビリティアナリストの取り組みを紹介しています。
5月16日:モビリティワーキンググループ(第4回)を開催
自動運転、ドローン、サービスロボットなど地域のモビリティを支える技術の事業化に向けた「モビリティ・ロードマップ2024(仮称)」の策定をするため、モビリティワーキンググループを開催しています。
第4回となる今回、「モビリティ・ロードマップ2024(仮称)」のとりまとめの方向性についてや、「AI時代における自動運転車の社会的ルールの在り方検討サブワーキンググループ」の検討状況について、意見交換をしました。
5月17日:マイナンバーカードを用いて本人確認をする事業者に、チェックポイント等を周知するための事務連絡を関係省庁に通知
マイナンバーカードを用いて本人確認をする事業者に、チェックポイント等を周知するための事務連絡を関係省庁に通知しました。
また、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)で無償提供しているICチップ読み取りを行うPCアプリの利用を推奨しています。デジタル庁でもICチップ読み取りを行うスマートフォンアプリの開発提供を検討していきます。
5月20日:デジタル庁ニュースで「AIで変わる行政サービス」に関する動画を公開
「AIで変わる行政サービス」を紹介する動画をデジタル庁ニュースで公開しました。デジタル庁参与でAI領域のエキスパートである上野山勝也が、生成AIの導入によって、行政と市民、行政組織内のコミュニケーションがどのように変化していくのかを紹介しています。
5月23日:デジタル社会推進本部が「デジタル・ニッポン2024」提言策定
5月23日に、自民党デジタル社会推進本部から「デジタル・ニッポン2024」をご提言いただきました。少子高齢化や人口減少など社会課題の解決、デジタル領域の産業振興、自然災害やサイバー攻撃対応など持続可能性の確保に向け、デジタル政策・データ戦略を着実に社会実装するとともに、デジタル庁の体制強化を図っていきます。
5月23日:マイナンバーカードの救急業務活用の実証事業を開始

マイナンバーカードの救急業務活用の実証実験を宮崎県都城市などで開始しました。救急車利用時に、マイナンバーカードを活用して救急業務をおこなうことで、救急業務の迅速化・円滑化を目的として、傷病者の医療機関への早期搬送と早期医療介入に結びつくことを目指しています。
河野デジタル大臣は、2024年5月26日にDXの各種取り組みを進める宮崎県都城市(都城市役所、北消防署)を視察しました。
都城市は、マイナンバーカードの普及率が全国トップクラスであり、「書かないワンストップ窓口」の実現、全国初の郵便局へのマイナンバーカード申請交付業務の委託等を実施してきました。全国に先駆けて「マイナ保険証」を活用して、救急搬送時に受診歴や薬の処方歴を取得する実証事業を進めています。
5月27日:マイナンバー法改正法が施行

2024年5月27日、マイナンバー法等改正法(改正マイナンバー法)が施行されました。これらの施行によって、大きく下記4点が変わります。
1.海外でマイナンバーカードを継続利用することが可能に
国外に転出(引越し)する場合に、マイナンバーカードが失効することなくお持ちいただけるようになりました。また、海外でもマイナンバーカードが作れるようになりました。
2.マイナンバーカードの「かざし利用」規定が明確に
マイナンバーカードの利用方法のうち、暗証番号を入力しない「かざし利用」に関する規定が明確化されました。今後も図書館カードとしての利用や避難所への入退場の際の利用など、「かざし利用」でのカード利用を推進していきます。
3.各種免許や国家資格等のオンライン・デジタル化へ
医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士をはじめ、80近い国家資格などの資格について、マイナポータルを通じてオンラインサービスを利用いただけるようになります。
4.公金受取口座の登録方法を拡充
日本年金機構と連携し、ご高齢の方やデジタルに不慣れな方でも年金受取口座を公金受取口座として簡易に登録可能になります。
デジタル庁noteで「改正マイナンバー法」に関する記事を掲載しました。国民の皆さまの利便性向上につながる主なポイントを4つご紹介しています。ぜひご覧ください。
5月27日:調整給付のための算定ツールの提供を開始
各自治体の調整給付ご担当者に向けて、給付を円滑かつ効率的に行うために、調整給付のための算定ツールの提供を開始しました。ご利用にあたり必要な各種資料およびご案内を掲載していますので、ご活用ください。
5月29日:テキスト生成AI利活用におけるリスクへの対策ガイドブック(α版)を公開
デジタル庁では、デジタル社会の実現に向けた重点計画を踏まえ、AIの実態と動向を把握し、リスクと必要な対応策を特定したうえで、官民における適切な活用の検討を進めています。
昨今の生成AIなどの技術革新により、さまざまな利点を得られるようになってきています。政府でも、このような技術の動向を見極めつつ、関係省庁における生成AIの業務利用について第10回デジタル社会推進会議幹事会・書面開催等の議論を重ねてきました。また、2023年12月より生成AIの適切な利活用に向けた技術検証を実施し、その結果を公開しました。
5月30日:デザインシステム専用サイト「デジタル庁デザインシステムβ版」を公開

行政・公共機関のウェブサイトやオンラインサービスでの利用を念頭に構築しているデジタル庁デザインシステムのガイドラインを、より参照しやすい形にするため、専用サイトを公開しました。
デザイン素材はこれまで通りFigmaデータで提供をしています。また、今後はReactのコードスニペットを順次展開して、作例を充実させていく予定です。ぜひご活用ください。
5月30日:マイナンバーカード機能のiPhoneへの搭載について
岸田総理大臣と米Apple社CEOのティム・クック氏の間でテレビ会談がおこなわれ、マイナンバーカードの機能をiPhoneに搭載することについて、確認がおこなわれました。iPhoneへの搭載の時期については、来年の春にリリースできるよう、取り組みを進めます。iPhoneへは、マイナンバーカードの機能のうち、現在Androidで搭載済みの、様々なオンライン申請やログインを可能とする電子証明書の機能だけでなく、マイナンバーカードの券面記載事項も搭載し、氏名、住所、年齢などを、オンラインでも対面でも、証明できるようにしていきます。
5月31日:国・地方ネットワークの将来像及び実現シナリオに関する検討会の最終報告書を公開
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(2023年6月9日閣議決定)を踏まえ、国・地方を通じたデジタル基盤に関して、全体最適かつ効率的なネットワーク構成を検討するため開催しており、この度検討会最終報告書を公開しました。
5月31日:令和6年度(2024年)PMH(医療費助成)先行実施事業の公募結果を公開
「令和6年度(2024年)PMH(医療費助成)先行実施事業」において、採択自治体を決定しました。医療費助成には、難病や障害など法律に基づき実施されるもの(公費負担医療制度)や、こどもやひとり親向けなど地方自治体が条例等に基づき実施するもの(地方単独事業)がありますが、マイナンバーカードをこれらの医療費助成の受給者証としても利用できるようにしていくために取り組んでいます。今後の全国展開に先駆けて、今年度から先行して取り組みを開始いただく153自治体・531制度を採択しました。また、自治体公募(二次)も開始いたしましたので公募要領を確認のうえ、ぜひ検討ください。
5月31日:ダッシュボードデザインの実践ガイドブックとチャート・コンポーネントライブラリ(ベータ版)を公開
ダッシュボード開発において品質向上や設計の効率化に貢献するため、実践ガイドブックとダッシュボード開発ツールのPowerBIのチャート・コンポーネントライブラリを公開しました。
実践ガイドブックは、デジタル庁で実践してきた政策データダッシュボードの作成時の知見に加え、行政職員や民間有識者のダッシュボードやデータ可視化に関する意見を反映したものを整理し、体系化したものです。今後もデータの可視化や分析に関する知見を公開し、EBPM(Evidence-based Policy Making)の推進を進めていきます。
さいごに
今回、2024年5月のデジタル庁の政策、サービス、組織に関する主な活動、およびプロジェクトの進捗や成果についてまとめました。
これからも、国民の皆さま、そして関係省庁や地方自治体の方々に政府のデジタル政策やデジタル庁の活動を知っていただくため、情報をオープンにする活動を進めていきます。ぜひ気になっていることなどございましたら、お声を聞かせてください。
■ご意見・ご要望はこちら
◆これまでの「デジタル庁からのお知らせ」記事は以下のリンクをご覧ください。

